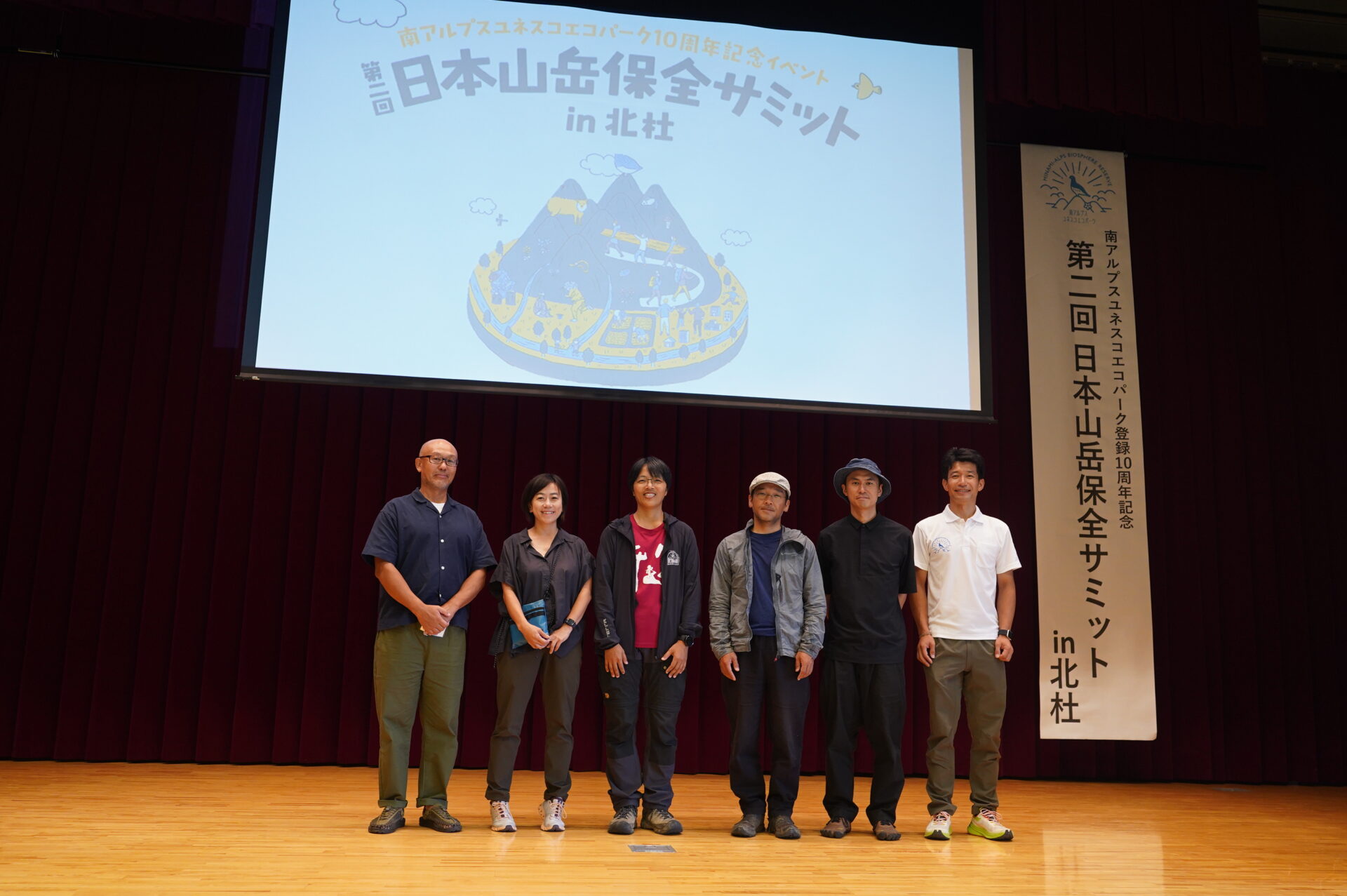2日目はシンポジウムを開催
2024年8月24日(土)から26日まで開催された「日本山岳保全サミットin北杜」。2日目は、会場を甲斐駒センターせせらぎに移して、シンポジウムが開催された。県内外から186名の参加者が集まった。株式会社ヤマップ代表・春山慶彦さんの基調講演、台湾千里歩道協会副執行長・徐銘謙(シュ・ミンチェン)さんの特別講演のあと、パネルディスカッションが行われた。
◆登壇者
株式会社ヤマップ代表取締役CEO 春山慶彦さん
台湾千里歩道協会副執行長 徐名謙さん
一般社団法人雲ノ平トレイルクラブ 代表理事 伊藤二朗さん
コンサベーション・アライアンス・ジャパン 代表理事 三浦務さん
一般社団法人北杜山守隊 代表理事 花谷泰広さん
【第2日目 / 午前の部】
はじめに、北杜山守隊の花谷泰広さんより開会の言葉が述べられた。「2日目は地域ごとにどういう取り組みができるのか、日本はこれからどのような方向を目指せばいいのかといったことを議論できればと思う。今日一日の体験を通して、会場の雰囲気が変わるのではないかと期待している」。続いて、上村英司・北杜市市長(2024年当時)からは「山を活用するだけでなく、しっかり保全することで10年後、100年後にも健全な状態が続くよう取り組んでいきたい。”ほくとの山2030年宣言in南アルプス”を宣言し、2030年までに南アルプスエリアにある市内の登山道をすべて修復することを目指している」との展望が語られた。その後、2日目のプログラムがスタート。以下、概要をまとめた。
特別講演
「流域の視点で見えてくる山の価値」
春山慶彦さん(株式会社ヤマップ代表)
◆流域の視点で見えてくる山の価値
今日お話しすることを結論から述べると「流域の視点で山を捉え直して、流域の視点で山をつくり直す」。山の保全を考えるとき、山を単体で捉えることが多いが、流域で捉えることで初めて山の価値が見えてくる。
◆なぜ流域に着目したか
近年、九州では毎年のように水害が起きている。2017年には九州北部豪雨が発生し、筑後川の朝倉地区が大きな被害を受けた。2020年には熊本県の球磨川で豪雨災害が発生した。これらは気候変動によるもので、これまでは「100年に一度」「10年に一度」といわれてきたような水害が、今後は毎年のように起こるかもしれない。それらを踏まえた上で、水との付き合い方を変えなければいけない時期に来ている。
気候変動と水とのつきあい方の変化について考えていたとき、養老孟司先生と岸由二先生の著書「環境を知るとはどういうことか〜流域思考のすすめ」(PHP研究所/2009年)に出合った。そのなかに「流域思考をベースにしたGoogleマップのような地図があればいいのに」という岸先生の言葉があり、ヤマップでつくろうと考え、3年かけて流域地図を完成させた。流域地図は、人間がつくった行政区分ではなく、水の流れで地域を捉えている。
◆流域地図の意味
山から水が下りて川になり、平地を通って海に注ぐのが流域。地球上では流域が入れ子の形で構成されている。地図はその時代に生きた人たちの世界観の象徴でもある。地図を変えることで、僕らの世界観を更新したいと考えた。水害を踏まえてどう暮らしを整えていくかという観点から世界観を更新するための地図が「流域地図」。
日本列島はそれぞれ流域圏でできている。昔の人はいま以上に水の流れを大事にしていた。たとえば甲斐駒ヶ岳は富士川水系の源流の山であるだけでなく、天竜川水系の源流の山でもある。甲斐駒ヶ岳が荒れるということは、その2つの水系が荒れるということ。だから僕らは山を保全する必要がある。洪水や浸水、土砂災害などのハザードマップも、流域の観点から作成する必要がある。
◆発信することで社会と接続する
探検家の角幡唯介さんが述べていたが、植村直己さんの時代は冒険という行為をするだけで表現になっていたため発信をしなくてもよかった。しかし、いまは社会が冒険や探検を求めていないため、それらを行うだけでなく文章や写真、映像などの表現に昇華して初めて社会と接続することができる。登山道整備なども同じで、活動の価値をどう社会に意味づけするかまで考えなければいけない。
◆登山道の保全は流域の保全
ある神社の宮司さんに「登山者は山を歩くけれど、山に何も返していない」と言われた。それは登山者が悪いということではなく、山との関わり方が少ないことを意味している。山を歩く以外の関わり方をつくることが重要で、登山道整備や保全はとても可能性があると考えている。
日本における山は本来、祈りの対象だった。それを流域の暮らしと繋げることができるのではないか。アメリカやヨーロッパの国立公園とは異なる日本の自然保全のやり方があるはずで、手入れや造園などを含め日本の自然観は人類の財産とも言うべき価値があると考えている。「登山道の保全は流域の保全であり、次の世代に残す風景をつくること」と言える。

クロストーク
春山慶彦さん×花谷泰広さん
花谷:北杜市には南アルプスのエコパークエリア、八ヶ岳エリア、瑞牆山のある甲武信エコパークという3つの大きな山塊があり、源流の山といえる。北杜山守隊はそのなかで甲斐駒ヶ岳を中心としたエリアで登山道保全を行っている。登山道保全に対して危機感を覚えたのは、2019年に発生した「令和元年東日本台風」。このとき、黒戸尾根の五合目の地面が抜けて、梯子が宙ぶらりんになり、すぐに対策を打たなければ黒戸尾根がなくなってしまうという危機感を覚えて修復に着手した。現状、まだまだ保全のスピードが追いついていないという焦りがある。登山道保全の活動は実際に行うと楽しい。トレイルランニングやロッククライミングと同じように、山のアクティビティのひとつになり得るのではいかと思っている。
春山:一度、登山道整備を経験すると、水の流れや現場にある材料でどう組み立てるかという観点で道を見るようになる。行為を通して自然とどう付き合っていくかを学んでいると感じる。登山道を整備することで水の流れが見えてくる。学校の教育に組み込んでも面白いと思う。
花谷:そういう意味でいえば、釣りの人たちは水の流れが見えていると思う。
春山:日本の自然観はユニーク。地震、津波、台風など、あらゆる自然災害を経験している。それが日本の「もののあわれ」や無常観に繫がっている。豊かで繊細な自然観を持っていて、貴重な財産だと思う。
欧州などの川はゆったりしているが、日本は山と海の距離が近いために川の流れが速い。この環境下で培った治水技術は世界に応用できるだろう。日本は「自然とは闘わない」という設定で構造物をつくってきた。たとえば筑後川にある山田堰は、川に対して斜めに堰をつくり、水を受け流すように設計してある。
花谷:甲斐駒ヶ岳も日向山も20年以上放置されていて、いろいろな場所が崩れて浸食していた。ところが20年以上前に施工したと思われる場所は崩れていなかった。おそらく、水の流れを受け流すようにして施工していたからで、昔の人たちの知恵が垣間見える。残念なことに、この20年間はその考え方を引き継げなかったが、岡崎哲三さんの方法論はそれらと繫がっている。
春山:宮大工の人たちも同じで、建造物をつくり変えるときに昔の宮大工のつくり方から学んでいる。伊勢神宮の式年遷宮が20年周期なのも同様ではないか。木造建築の技術を継承するためには20年というサイクルに意味があるように思う。その間に人を育てて、技術を継承している。同じ考え方で登山道整備の制度をつくれば日本らしいと思う。

主な質疑応答
<質問>
流域に暮らす人たちに山と流域に関心を持ってもらうにはどうしたらいいか。
◆回答
花谷:川や海で活動している人たちと連携できないかと考えている。
春山:食に落とすのがいちばんいいのではないか。概念で語ってもなかなか理解されないが、「美味しい」と感じると理解しやすくなる。将来的には流域をテーマにした場所をつくり、流域を象徴したレストランをつくりたいと考えている。流域の食にはいろいろあるが、もっともわかりやすいのは牡蠣。牡蠣の漁師さんは森の大切さを深く理解している。美味しい牡蠣を食べた人はその体験を忘れない。そのほかに日本酒なども、流域を象徴すると思う。
<質問>
企業はどう流域と関われるのだろうか。
◆回答
春山:企業は本拠地の場所に関わる取り組みを行うのがよいのではないだろうか。それに対して税制優遇など行政がインセンティブをつくることで、企業も興味を持つようになると思う。
花谷:制度の問題が重要。アメリカでは寄付が多いが、それは寄付を行った企業にインセンティブがあるから。ローカルの団体としては、支援してくれた企業や人に対してアクティビティを用意できると思う。まだそこまでの段階に至っていないのは、行政の制度設計が追いついていないからだと感じる。
<質問>
太陽光パネルとトレイルランについての意見を伺いたい。
◆回答
春山:流域の観点がないために、山の斜面に太陽光パネルをつくってしまうのだと思う。九州でも増えていて、地元企業ではない企業が参入している。地域に対しての愛がないし、それを許してしまっている状況にも問題がある。上流でのインパクトは土砂災害などに繫がる。しかしエネルギーは必要なので、都市の屋根など設置場所を考えるべきだと思う。
花谷:トレイルランについて。黒戸尾根はトレイルランニングが盛んで、それにより踏圧の進行も多少は見受けられる。ただ、トレイルランナーに限らず、登山者も登山道について知らないことが多いので、ワークショップでは半日かけて自然観察を行い、人の導線と登山道のえぐれ方の関係について考える時間を設けている。登山者の方が重い靴を履き、人数も多いので、トレイルランナーだけが悪というのはどうかと思う。一方で、トレイルランの大会はインパクトがある。それを大会主催者や参加するトレイルランナーが理解していることが大事だと思う。
【第2日目 / 午後の部】
基調講演
「台湾千里歩道協会の取り組み」
徐銘謙さん(台湾千里歩道協会 副執行長)
謝琪薏さん(通訳)
◆まず海外の事例を学んだ
台湾には費用をかけた割に耐久性が高いとはいえない登山道が多くある。環境や生態系に対しての破壊も進んでいる。私自身は2002年から登山道保全に取り組むようになった。2006年には米国アパラチアントレイルに赴き、現地の保全活動について学んだ。アメリカ以外にもアイスランド、イギリス、ニュージーランドなどの事例から学びを得た。
2002年、近自然河川工法の第一人者である福留脩文先生が台湾を訪れ、いろいろな話をした。2018年には福留先生が活動する屋久島を見学し、2019年は大雪山で岡崎哲三さんの活動を視察した。これらの経験を通して、国ごとに制度や環境、保全活動の方法が異なることを感じた。
◆台湾に適切な方法とは何か
こうした経験を踏まえた上で、私たちは台湾に合う方法を考えた。登山道の保全活動では、一般参加者を募り、子どもたちにも多く参加してもらいたいと思った。行政の協力も欠かせない。2009年「手作り歩道」という名称を決め、コンセプトと方針を策定。官民連携で推進することした。
◆4つの主な技術タイプ
技術タイプは主に4つに分けられる。1.国家征服モデル 2.地域自給モデル 3.国家景観モデル 4.公民参加モデル。これまでは「地域自給モデル」が多かったが、30年前から増えてきたのが「国家景観モデル」で、ここでは土木建設に費用をかけている。「地域自給モデル」は歩きやすさを考えてつくられており、その土地の自然環境に合わせて、近場にある資材を用いて行う特徴がある。
台湾は日本統治時代を経験しているため、かつては政府がまとまった予算を投じて軍事目的の道をつくっていた。いまもそれらの古道がたくさん残っており、どう修復していくべきか考えている。日本と同じように台湾も人口が減少しているため、永続的な保全を行うには、外部から人を集めることが大事であり、専門家も呼ぶ必要がある。
◆歩道ワーキングホリデーの運用
最初に展開したのはエコツーリズムのポテンシャルがある地域でのワーキングホリデー。たとえば2泊3日で、古い集落に住んでいる人たちが受け継いできた知恵を学んでいく。エコツーリズム体験とボランティア活動によって、その地域への共感が深まる。山に入ることがただの環境消費ではなくて、参加型の環境産業になっていく。地域で継続的に活動していくことで、結果的にトレイル保全活動に繫がっていくのではないかと考えている。
歩道ワーキングホリデーは、エコツアーとボランティア活動の2つが主軸で、入門推進型、労働体験型、サービス学習型、社会貢献型に分かれている。それぞれ労働の度合いや、工事の難易度がレベル分けされており、日帰りから3泊4日まで設定している。
◆歩道工法設計マニュアルを作成
主に専門家に向けて「歩道工法設計マニュアル」を作成した。20年間の活動経験を活かし、手作り歩道の手法をまとめたもので、台湾の国立公園の工事でも採用されている。
まず、よくある歩道問題を15に分け、それらを5つの主要な環境要因と27のサブカテゴリーで分類した。また、これらの問題に対して対応できる10の主要な工事項目と92の工法タイプを洗い出している。40通りの工法図説も掲載している。
◆専門家の育成に注力
専門家を育成するプログラムとして「歩道学」という学習カリキュラムを作成している。ここでは自然科学、工程科学、社会科学、人文科学などを学ぶ。5つのカテゴリーに分け、3つのレベルで学ぶ仕組み。すべての人がすべてを学ぶ必要はないと考えている。
レベルが上がり、活動意欲が高そうな人たちには声をかけ、さらに学習を重ねてもらう。ランクは5段階あり、最上位は名誉歩道師で、その下にベテラン歩道師、歩道師、実習歩道師、種子歩道師と続く。ベテラン歩道師が評価していく仕組み。
2023年時点で、名誉歩道師12名、ベテラン歩道師3名、歩道師8名、実習歩道師22名、種子歩道師46名が所属している。これまでボランティアに参加した人は14727名。17年間の活動をとおして、170本の歩道を修復し、稼働時間は1085日に及んでいる。

パネルディスカッション
徐銘謙さん、伊藤二朗さん、春山慶彦さん、三浦務さん、花谷泰広さん
三浦:私が所属する CAJ(コンサベーション・アライアンス・ジャパン)では、2023年に開催された「第1回日本山岳保全サミットin大雪山」から助成金を支援している。今回の支援金を活用して、台湾から徐銘謙さんをお招きすると花谷さんから聞き、素晴らしいと思った。先ほど、徐さんから台湾での20年に渡る活動やそのノウハウを伺ったが、おそらく目指しているゴールは私たちと同じだろう。このイベントが知見を共有できる機会となり嬉しく思っている。
◆技術者育成の体系化をどうするか
春山:今日は単に対話するだけでなく、提言をまとめるところまで持っていきたい。除さんの話を聞いて、どのような印象を持ったか。
伊藤:活動しているエリアについて、行政との絡み、スタートラインがどうだったのか気になった。日本は地域ごとに体制が異なるなど、より複雑だと認識している。行政区分はどうなっているのだろうか。日本は非常に障害が多いのだが。
徐:地域ごとに異なるので、いろいろなケースがある。台湾でも障害は多く、行政は日本と同じように縦割りの傾向にある。
春山:花谷さんが徐さんを招いたきっかけは?
花:僕は観光型のワークショップが成り立つのではいかという仮説を立てていた。そこには日本人だけでなく、台湾など海外からも参加してもらいたいと思っていた。そんなとき、北杜山守隊のワークショップに台湾から登山愛好者が2名参加してくれた。その方たちが「台湾でも同じような活動をしている団体がある」と千里歩道協会について教えてくれた。実際に台湾を訪れて活動を見学させてもらったところ、スタートしたばかりの北杜山守隊とは大きな差があることを感じた。
いま僕らが行っているワークショップは、台湾を参考にしている。すごく近いところに、日本が目指すべき将来のヒントがあるのではないかと思い、ぜひ皆さんとシェアしたかった。もっとも紹介したかったのは技術者育成の体系化。日本では各地で独学の人が増えているので、一本化していかなければいけないと感じている。
春山:日本山岳歩道協会を立ち上げた理由もそこにある。人材、費用、事業、情報の4つをどう制度として設計して回していくかがゴールだと思う。最終的には行政の制度として落としていくことが大事だろう。なかでもキーになるのは技術者の育成。現状は学ぶ方法が散在しているため、その受け皿として日本山岳歩道協会をつくった。これをどう人材育成に繋げていくかは今後チャレンジしていくべきことだと思う。
◆ロールモデルをつくる
伊藤:雲ノ平トレイルクラブでは不特定多数のボランティアを集めるのではなく、基本的には技術者を育てるスタンスで人を集めている。それぞれの得意分野を活かした自律的チームを目指している。雲ノ平は、アクセスが難しいという地理的な特徴があり、その分コストがかかる。
春山:県市町村単位でロールモデルをつくり、横展開していくのがコンセンサスを取りやすいのではいか?
花谷:全国各地で一律に同じことはできないと思う。たとえば北杜は首都圏から2時間ちょっとで訪れることができるので、人を巻き込みやすい。ワークショップを通して、地域や自然、歴史について学び、実際に作業もしてもらっている。参加者の半数はその後、会員登録している。都市に近いところであれば同じような展開できるはずなので、「北杜モデル」を真似してもらえればと思う。
春山:除さんへ。いまあらためて着手するなら、こうしただろうというイメージはあるか?
徐:もしやり直すことになっても、現状はどうなっているのか、過去に何があったのかを整理していくと思う。地域の特徴は何か、課題は何か、制度は何かを見ていく。活動に関しては、一回一回のチャンスに対して、きちんとプロとして表現していくことがとても大事だと考えている。行政が2回のチャンスをくれるとは限らないから。
春山:将来、徐さんの後任に就くような人はいるのか?
徐:私自身は明日にでもリタイアしたい。ここ数年、毎日ように歩道学について語る日々を過ごしてきた。もっと教えられる人が増えていけば広がりも生まれるのではと思う。
春山:除さんの考え方はどんな事業にも当てはまると思う。現状を分析した上で過去を振り返り、未来を設定して一つずつ詰めていく。日本の現状も決してダメなわけではなくて、さまざまなピースがバラバラになっている状態。それらをテーブルに上げれば議論もできるが、まだまだ整理ができていない。まずはテーブルに並べて議論することが契機になると思うので、そういう意味でCAJの役割は大きい。
三浦:自分はCAJとNPO法人富士トレイルランナーズクラブの両方に所属しているので立場が混在しているが、CAJとしてみれば、違う立場の人たちが議論しながら地域の活動を進めていくことが大事だと思う。しかし実際にそれを現場で実現できるかというと難しい。日本人は議論が得意でないことも要因のひとつだろう。
春山:産官学民間が連携しながら、過去と未来を合わせ鏡のようにして、まとまっていくこと。アウトドア企業の支援、行政の支援など、活動する人たちを応援するプログラムをつくっていく。台湾の取り組みを参考にしながら、日本でもこういった取り組みに発展させていきたい。

主な質疑応答
<質問>
除さんの未来設計図を教えてほしい。
◆回答
徐:自然のなかで働く人たち「グリーンカラー」を推奨していきたい。山に限らず自然や地球を守りたい、次の世代に繋げたいという思いを持つ人たちがフィールドで働けるような環境を整えていきたい。
<質問>
資格について。近自然工法について環境省などが取り上げて議論し始めたのは2000年頃から。20年経過するが、いまだに技術が体系化されていない。これらが資格化されれば、人材育成や財源確保のブレイクスルーになるかかもしれない。そのあたりはどう考えているのだろうか?
花谷:資格化は進めていくべきだと思う。たとえば山岳ガイドが資格化したのは、比較的最近のこと。ガイド資格がそうだったように、その資格をとれば仕事ができるというプロセスをつくっていくことは必要。台湾の事例を参考にして、資格化を進めた方がいいと思う。まずは団体が資格の認定を行い、規模が大きくなってきたら国家資格の議論が始まってくるのではないかと思う。
伊藤:資格化はひとつの選択肢ではあるが、唯一の答えではないと思う。海外には地方や国立公園、団体単位の基準や人材育成システムがあり、日本の場合はそちらのイメージが近いように思う。
◆ディスカッションの最後に
徐:この2日間で山を守る団体の皆さんのお話を聞くことができた。この山岳サミットの開催も含めて、日本では次々に新しい歩みが始まっているのを実感した。まだまだたくさん課題はあるが、山歩きと同じように一歩一歩進んでいけば目指している方向に向かっていくと思う。これからの展開を楽しみにしている。
花谷:冒頭で「今日一日が終わったときに会場の空気が変わっていれば」と述べたが、本当にそうなったのではないかと思う。このイベントに興味を持ってくださった方たちと現状の共有ができたのではないか。決して簡単な問題ではないが、一つひとつ議論を重ねて進めていきたい。
閉会の挨拶
北杜市南アルプスユネスコエコパーク地域連絡会副会長・溝口克己氏より閉会の言葉が述べられ、2日目のイベントが終了した。
文◎千葉弓子
写真◎北杜山守隊